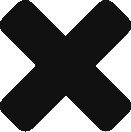晩夏のいわき
バスの座席に座り定刻を待っている時、運転手が「今日は暑いのでエアコンつけますね〜」と言いスイッチを入れた。ゴォーという音と共に冷気がふんわりとうなじと肩のあたりに降ってきた。
13:00になり、バスは動き出した。運転手が行き先を告げる。「当バスはこうせん経由、〜〜行きです」。それを聞いた時、心の中で(こうせん?こうせんて今から俺が行こうとしてる鉱泉のことだろうか…それとも専門高校的な方の高専だろうか…もし前者であれば歩かなくていいぞ…!しっかり耳を澄ましておかねば)と思った。聞き逃しては大変なので、いつも移動中に着けるイヤフォンも着けずに耳を運転手の方へ向け、前のめりで音に集中した。
道中窓の外を無意識に眺めていると、秋の穏やかな空と並ぶ住宅の中に突然宇宙船のような建造物が現れた。なんだこれ!と思ったと同時にすぐ、運転手の「次は競輪場前、競輪場前〜」という答えが聞こえた。
片道20分ほどの道のりだっただろうか。今か今かと“こうせん”を待つ。ついにその時が来た。「次は松〜高専、松〜高専ですー」。なんだ高校の方か~~と少しガッカリし、緊張状態だった身体中の力は抜け、座席にズアッと背中を預けた。結局元来の目的地であるショッピングモールの到着を待つことになった。
これはいわき、引いては福島に限らず、自分の田舎や他の地方でも同じ話だが、バスが高い。逆に東京は安い。多分客が多いからなせることなんだろうけど、固定額というのも地味に凄いことだ。地方バスはただ高いだけではなく、番号が振ってある整理券と、その番号に合わせて天井知らずで上がり続ける運賃のコンボも凶悪なのである。
そんなくだらない恐怖を感じつつ窓の外をボーッと眺めていたら、目的地のモールに着いた。モールから歩いて10分という時点で当たり前だが、周りは住宅がミッシリ並んでいるのには拍子抜けした。安宿誌の荒い白黒写真で見る分には、山林の中に佇む秘湯といった趣を勝手に感じていたからだ。というかホントにこんなところに鉱泉宿なんかあるんだろうかと、逆に場違いに思えるほどだった。グーグルマップを頼りに、モールを横断し大胆なショートカットをしつつ、7、8分も歩くと吉野谷鉱泉と書かれた看板が目に入った。説明文を読むと、周辺の住宅地の中央に位置する自然豊かな緑地帯、さらにその中央にその鉱泉は位置するようで、開湯されたのは江戸時代らしかった。ここだ!と思い、看板のすぐ横から伸びる、千と千尋の湯屋への道のような緑茂る道を進んで行った。途中左手に鍵の間にキラキラ光るものを感じたが、それは池の水面に反射する太陽光で、鴨たちがグワグワとのどかに遊泳していた。鴨たちを横目に更に100メートルほど行くと、並ぶ椰子の木の奥に趣のある日本家屋が見えてきた。着いた!とそれまで若干低空飛行気味だったテンションが上昇してきた。

数棟の家屋たちへの入口には、“吉野谷鉱泉 1泊4200円”という看板が立っており、長期滞在割引もあるらしく、湯治宿としても使えそうだった。駐車場には車が2台停めてあり、あ、ちゃんと客がいるんだ、と少し安心しつつ、恐る恐る受付と思わしき引き戸ーメインエントランスーを申し訳程度にコンコンと中指の第二関節で叩いた後、ガラーと開けた。中に入ってみると、人の気配はあるがヒッソリとしている。呼び鈴でもあったかな、と周りを見回し始めた時、入口から伸びている廊下の奥から、主人らしきおじさんがノソノソと歩いてきた。「こんにちは〜」「あ、こんにちはっ。今日予約している湯渕です。」「はいはい、ちょっとお待ちくださいね。どうぞ、上がってください。スリッパそちらにありますんで。」「ありがとうございます、失礼します」少し不意打ちでもあったので、多少の不要な焦りを交えつつ、土間から客間の方へ上がった。「湯渕さんね。じゃあこの用紙に諸々書き込んでください」手渡されたプリント紙に個人情報を書き込む。「はいどうも。あとで色々案内するんですけど、ちょっと準備があるから少しここで待っててもらえる?」「あ、分かりました」少しの間をおいて、ご主人がまた話し始めた。「あのね、私は作家なんですよ」「えっ、そうなんですか?」「はい、小説なんかも書きましたし、あとは戦争や日本の防衛に関する本なんかを出してます。私の名前で調べたらインターネットに出てきますよ」「えぇ〜すごい」「日本はアメリカに国力で負けたなんて言ってますけど、そんなことではないんです。最も重要なことは研究力です。特攻隊を分けたのが良くなかった。あれを一回まとめて突っ込んでいればまだ勝機はあったかもしれない」「え、そうなんですか?」大胆な主張にギョッとしてしまった。「うん、だって小分けにしたらあっち側も「こういう手で来たか、ならこういう対応策を取ろう」ってなるでしょ?」「あぁーそれは確かにそうかもしれませんね」「あと昔サリン事件てあったでしょ?」「あ、ありましたね」先程の発言に加えてセンシティブな話題ということもあり、ぐっと唾を飲んだ。「あれも東京中にもっと一気大量に撒いてたらもっと被害は与えられたんですよ」「は、はあ」「オウムは最初ヘリを使って空からもサリンを撒くよていだったらしいんですけどね、なんで辞めたんだろうね」「いや〜、怖いですねぇ…」またも不意打ちを喰らった。まさかこんなカジュアルにこんなハードな話を聞くことになるとは。話が一区切りしたところで、奥から従業員らしき女性が歩いてきて「いらっしゃいませ」と軽く挨拶をしてきた。同時に主人が「はい、準備ができましたので行きましょうか」と廊下の方へ手で促した。

渋さ極まる宿
誰もが思い描くようなザ・田舎の古民家の板張りの廊下を主人について行く。中庭を囲むようにコの字型に大まかに3棟の建物が連なっているので、窓からは中庭を通して向かいの建物が見えるようになっている。その中庭には小柄な数本の枯れ木と、それらに囲まれるように中央に黄色い花ー植物に詳しくないので種類が分からないーが咲いており、全体的に彩度の低い景色の中のアクセントのようであった。建物間の繋ぎ目の渡り廊下ーといっても列車の連結部のような短さだがーを渡り別の家に入ると、「こちらが客室になります」と主人。どうやらこの家にメインの客室が集まっているらしかった。それぞれの部屋の引き戸の上には木の板が打ち付けられており、なにやら手書きで文字が書いてある。読んでみるとそれぞれ部屋の名前らしく、牡丹、紫陽花、薔薇など、花の名前で統一されているようだった。「今日は全部空いてるのでお好きなお部屋選んでください」そう言いながら主人がそれぞれの部屋の引き戸を開けていく。「こちらは布団タイプ、こちらはベッドタイプの部屋ですね」“薔薇”はベッドタイプで、なるほど、これらの花の中では洋風の感があるなと少し可愛らしく思った。しかし折角こういう和風の宿なので、ここはベッドでは味気無いと思い、「“紫陽花”でお願いします」と布団部屋を選んだ。
案内はここでは終わらず、次はこの宿の核でもある鉱泉の使用法の説明を受けた。温泉というものには幼き頃より慣れ親しんできたが、鉱泉というものには東京の上野にあるものに一度入ったくらいで、その時は鉱泉と温泉の違いも全く知らず、その上野の鉱泉がえらく熱かったのもあり、鉱泉とは温泉よりさらに熱い風呂、という完全に間違った認識が残った程度であった。実際には鉱泉はむしろ冷たい。冷たい水に温泉に入っているような成分が入っているので、それを温めて入浴できるようにしているのだ。かなり荒々しい説明はここらへんにして、詳しい説明はネットにいくらでも転がっているので、そちらで参照していただければと思う。この吉野谷鉱泉の成分や泉質・・・その類の情報は全く見ていなかった。これもネットにあるかもしれないので、そちらで確認していただきたい。主人に教えてもらったのは、時間によって使える湯舟ー二つあるが一度に使えるのは一つー、女専用か混浴、泊り客か立ち寄り客、などの入れ替わりが発生するということだった。あと湯を沸かしてほしいときは、浴室のある建物の裏に向かって「もっと湯を沸かせ」と指示しろとも教えられた。どういうことかと言えば、声をかければ従業員の方が火を焚き湯を沸かしてくれるという、まるで昔の殿様のごときシステムなのである。しかも声をかけても反応が無い時は、脱衣所においてある鐘を打ち鳴らせばその音は宿全体に鳴り響き、すぐ従業員が駆けつけるらしい。そんなでかい音を鳴らして他の客などの迷惑にならないのかと一瞬憂慮したが、入浴できる時間は19時までと比較的浅い時間までなので、ギリギリ大丈夫なのかもと思い直した。
主人は一通り宿の説明を終え、自分は”紫陽花”へ戻った。六畳の畳の和室、入って左手に布団が敷かれ、その手前に鏡台、右手にはこたつとその奥にはテレビとヒーターと、コンパクトながら日本人に必要なものが全て揃っており、ミニマリストならこんな部屋で長期滞在するなんてのも良いんだろうな、などと思ったりした。普段洋室でベッド暮らしというのもあり、和室と布団というのは新鮮でもありながら、やはり大変落ち着く。荷解きをし、本や充電器などをこたつの上に置き、布団に寝転んだ。いや〜いいもんだ、と一息つきつつ、持ってきたつげ義春の“貧困旅行記”の続きを読み始めた。この本は今回の安宿旅のきっかけのひとつにもなった本で、つげさんの独特の感性を通して一昔前の旅の様子が思い浮かべられ、大変好きな本なのであった。つげさんの感性はところどころ「そういうこと感じるか〜」と斬新さもありつつ、割とシンパシーも感じやすい。それは恐らく彼の感覚が割と現代の若い世代と似ているからかもしれない。かなり偏見ではあるが、自分は今の高齢者というのはイケイケどんどんで団体主義で個人個人の内面性なんていうのは二の次三の次、といった印象を持っていた。しかしつげさんの本を読む中で、もちろん彼らにもそれぞれ喜怒哀楽、楽しさや苦しさはあったわけで、それを乗り越えつつ突き進んできたからそういった面が見えにくくなっていたのかもと気付いたりした。特に彼は作家ということもあり、感受性が団体より個として突出しているというのもあるかもしれない。あと書きながら思い出したが、昔“吾輩は猫である”を読んだ時にも同じことを感じた。割と現代人(特に陰キャ)と同じ感覚だったんだなと。

話が逸れてしまったので宿に意識を戻す。そんな感じで貧困旅行記を読んでいると、コンコンと戸の横の柱?を叩く音が聞こえ、開けるとまた違うおじさんが立っていた。先程の主人より幾分長身だが、同じように眼鏡をかけている。
その2へ続く…